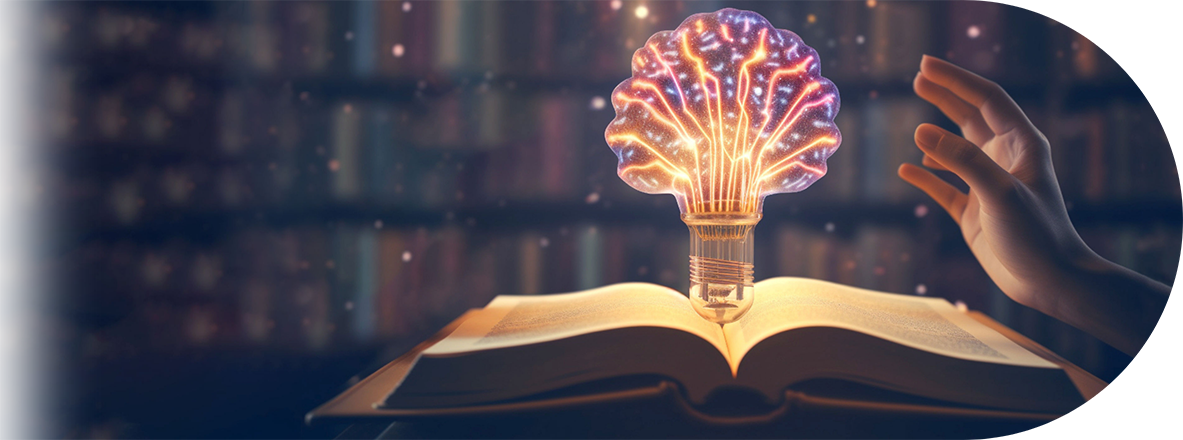<第3回> 効果的なインテリジェンス実装の進め方
2025.7.8
丸貴 徹庸
近年、目まぐるしい環境変化に対応し成長することが企業に求められる中、外部情報を迅速に収集し、意思決定に生かすインテリジェンス機能の重要性が増しています。当社の支援事例を踏まえ、インテリジェンス業務を推進する際のポイントを、連載コラム「インテリジェンス基盤」としてお伝えします。
■連載コラムでわかること(予定)
- 第1回:事業環境変化への適応に向けたインテリジェンス機能の組織への実装
- 第2回:組織のインテリジェンス機能におけるAI技術の活用
- 第3回~:効果的なインテリジェンス実装の進め方
※各記事のテーマは変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
「必要性は分かっている。では、何から手を付けようか?」
本連載コラムではこれまで、インテリジェンス機能の概要(第1回)、AIによる高度化のポイント(第2回)を述べてきました。第3回ではインテリジェンス機能を組織へ効果的に実装する進め方について、私たちのコンサルティングの現場で得られた知見をもとに、実践的なヒントをお伝えします。
本連載コラムではこれまで、インテリジェンス機能の概要(第1回)、AIによる高度化のポイント(第2回)を述べてきました。第3回ではインテリジェンス機能を組織へ効果的に実装する進め方について、私たちのコンサルティングの現場で得られた知見をもとに、実践的なヒントをお伝えします。
インテリジェンス基盤構築5つの論点
いまや生成AIの活用がビジネスのトレンドとなっていますが、いきなりAIに全て頼ることはできません。(1)ブラックボックスではなく、腹落ち感がなければ判断できない、(2)一般論を追求してもしかたがない、我が社固有の価値観や意思を反映しなければ意味がない、(3)他の事例や知見とも結びつけ、柔軟な発想の転換、時には発想の飛躍が必要、(4)網羅的な情報の列挙ではなく、的確に抽象化しなければ議論できない。このような問題を回避するために、まず以下に示す5つの論点をクリアにすることが重要です。
 出所:株式会社 三菱総合研究所
出所:株式会社 三菱総合研究所
事業ポートフォリオの評価、主力事業のコントロール、ロビイング活動、ブランディング、これら目的に応じて分析する情報の粒度やアウトプットの質、頻度などが変わってきます。そして最も重要なのは時間軸の視点と言えます。足元の脅威と、大きな変革の中での機会の捕捉とでは、分析のフレームワークが異なります。親会社の立場と、事業会社や事業部門としての役割を整理しておかなければ、インテリジェンス機能を担う組織は混乱を来すでしょう。目指す姿に最適な情報基盤のあり方の議論も必要です。潤沢に人手をかけられず省人化を目指すためにも、インテリジェンス基盤は情報システム基盤と密接に関係します。一夜にして夢のような基盤も整備できません。確りとしたマイルストーンを持たなければいけません。
それぞれの論点について自社の現状を見極め、最短の取り組みの戦略を立てることが求められます。
それぞれの論点について自社の現状を見極め、最短の取り組みの戦略を立てることが求められます。
 出所:株式会社 三菱総合研究所
出所:株式会社 三菱総合研究所
組織知を形式知化する「テーママップ」の作成
テーママップについては第1回で触れましたが、ここではその意義を説明します。
組織が意思決定をする際、関係者の間には所管する範囲、立場、これまでの経験によって多様な見解が存在し、時に衝突もします。結論に至るためには、経営、現業部門、インテリジェンス担当組織の間で認識を共有することが必要です。属人的な解釈の上に成り立った活動では持続的とは言えません。組織が考えるインテリジェンスの共通言語化が、テーママップの作成です。
組織が意思決定をする際、関係者の間には所管する範囲、立場、これまでの経験によって多様な見解が存在し、時に衝突もします。結論に至るためには、経営、現業部門、インテリジェンス担当組織の間で認識を共有することが必要です。属人的な解釈の上に成り立った活動では持続的とは言えません。組織が考えるインテリジェンスの共通言語化が、テーママップの作成です。
 出所:株式会社 三菱総合研究所
出所:株式会社 三菱総合研究所
テーママップは上図に示すように3つの階層を持ち、最上位の第3階層が企業に影響を与える具体的なテーマ、最下層の第1階層が一般的なマクロ動向となります。当社の重要な関心事である原材料の調達(第3階層)は、輸出入規制や争奪といったシナリオの想定幅(第2階層)に影響を受け、シナリオが動く予兆を把握する目的でマクロ動向(第1階層)を観測する、などと整理できます。企業の関心事(第3階層)とシナリオの考え方(第2階層)によって、企業ごとにオリジナルなテーママップが完成します。
拠り所となる考え方を明らかにすることで外部環境への理解が深まります。テーママップは固定的ではなく、ビジネスモデルの変化やゲームチェンジャーの出現によってメンテナンスをしていく必要があります。本質を逃さずに分析の説明力を向上させるテーママップの作成は、インテリジェンス実装の入口として非常に重要です。
テーママップ作成後の活動例と効果
まずは初版のテーママップを活用したインテリジェンス活動の端緒となる取り組み事例を紹介します。
① 経営会議の高度化
取締役会や経営会議で、中長期のビジョンの議論に乏しいと伺います。四半期単位でテーママップに沿って、特に第2階層に注目し、経営または事業責任者として備えておくべき世界の「幅」を議論します。世界情勢の解釈を共有し、戦略分野の軌道修正や選択肢の持ち方、ノンオーガニックな成長機会の探索などの議論の質を高め、事業部門とコーポレート部門との健全な牽制関係を構築します。
② バックキャストの検証
長期ビジョンからバックキャストで作成した事業計画について、描いていたシナリオが本当にその方向に向かっているのか(第2階層)、黄信号や赤信号が点灯しているのであれば何が問題となるのか(第3階層)を察知することで事業ポートフォリオを評価し、戦略領域へのリソース投入を進める、逆に引き締める、異なる領域を強化しておくといったリソース配分へ反映します。